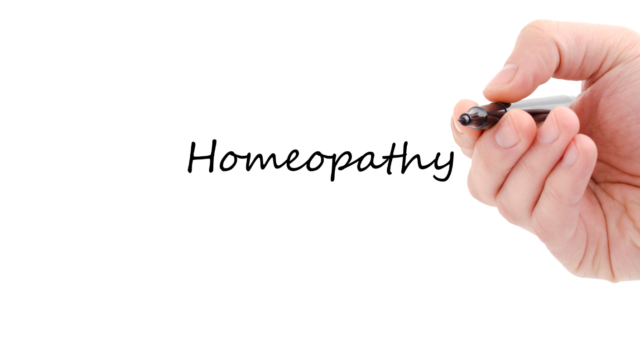こんにちは。ホメオパシー療法家の岩崎健寿です。
わたしはこれまで精神的な不調をもつ人たちの支援に長くかかわってきました。
その経験から、精神の安定を図るために眠りはとても大切であることがわかりました。
眠らない動物はいないと言われるほど、当たり前の生理機能ですが、眠りに関する多くの部分は未だ解明されず、謎に包まれたままです。
科学の進歩とともに不眠への対処方法は選択肢が増えました。
その一つが、睡眠薬の服用です。
Contents
不眠症と診断される基準を教えてください
誰しも多かれ少なかれ眠れないときはあると思います。
ですが長期間不眠がつづき、だるさ・やる気のなさ・集中困難・
診断ポイントは2つ。
①夜間不眠がつづくこと
②心身の不調によるQOL(生活の質)低下
不眠と日中の不調が週に3日以上あって、
睡眠薬にはどんなものがありますか?
一言に睡眠薬といっても、大きく分けて2種類あります。
睡眠薬の種類
睡眠導入剤
→医療機関で医師の診察の上で処方されるもの。
睡眠改善薬
→ドラッグストアなどで購入できるもの。
睡眠改善薬の場合、抗ヒスタミンによって眠気を誘うので、
睡眠導入剤の種類
現在、不眠を訴えて医療機関で処方される睡眠導入剤は4種類です。
①ベンゾジアゼピン系
②非ベンゾジアゼピン系
③メラトニン受容体作動薬
④オレキシン受容体拮抗薬
ベンゾジアゼピン系は、
日本では約50年前から使われています。
種類も多くて、効き目の短いものから長いものまであります。
しかし、ふらつきなどの副作用が出やすく、
| 作用時間 | 分類 | 一般名(商品名) |
| 超短時間 | メラトニン受容体作動薬 | ラメルテオン(ロレゼム) |
| 非ベンゾジアゼピン系 | ゾルピデム(マイスリー) | |
| ゾピクロン(アモバン) | ||
| エスゾピクロン(ルネスタ) | ||
| ベンゾジアゼピン系 | トリアゾラム(ハルシオン) | |
| 短時間 | ベンゾジアゼピン系 | エチゾラム(デパス) |
| ブロチゾラム(レンドルミン) | ||
| リルマゾホン(リスミー) | ||
| ロルメタゼパム(エバミール、ロラメット) | ||
| 中間作用 | オレキシン受容体遮断薬 | スボレキサント(ベルソムラ) |
| ベンゾジアゼピン系 | フルニトラゼパム(サイレース) | |
| エスタゾラム(ユーロジン) | ||
| ニトラゼパム(ベンザリン、ネルボン) | ||
| 長時間 | ベンゾジアゼピン系 | クアゼパム(ドラール) |
| フルラゼパム(ダルメート) | ||
| ハルキサゾラム(ソメリン) |
もし今現在、睡眠導入剤を服用している場合は、
欧米と日本で薬の処方に違いはありますか?
欧米と日本では睡眠導入剤に対する認識が異なるようです。
欧米では日本ほど簡単には処方してもらえません。
まずは、生活習慣の改善。
それでもなお、改善しない場合のみ薬が処方されます。
欧米のほうが薬の処方に対しては慎重です。
これは依存の危険性を重視しているからと言えるでしょう。
睡眠導入剤は飲みつづけているとその状態に体が慣れてしまい、
特に、依存度を強化してしまう「退薬症候」には注意しなければなりません。
退薬症候とは?
身体的に依存しやすい薬を長い間飲んでいて、
具体的には 不安、不眠、焦燥感、ふるえ、発汗などの症状があらわれます。
退薬症候を起こさないためにできることはありますか?
一つは、いきなり減薬したり止めないことです。
これは処方してくれる主治医とよく話し合って、少しずつ減薬していってください。
二つ目に、なぜ不眠がつづくのか?
不眠に至ってしまった原因を探りましょう。
不眠になる原因
①ストレス
②からだの病気
③こころの病気
④薬・嗜好品(刺激物)
⑤生活リズムの乱れ
⑥環境
⑦その他(睡眠時無呼吸症候群やムズムズ病など)
以上の項目の中でも、一人ひとりの背景は異なるはずです。
問題を解決するためには、
眠れないからと言って、
不眠の改善には、背景因子の改善が一番の近道です。
薬を飲む以外に眠る方法はありますか?
薬との相性は個人差があり、千差万別です。
あなたが訴える内容と主治医の認識に微妙なズレが生じる場合も少なくありません。
そこで、まずはご自身でできることを試してみましょう。
すぐに効果があらわれるとは限りません。
長い目で見て、毎日コツコツ継続していきましょう。
自然な眠りのためにできること
①規則正しい生活リズム。
②日の光を浴びる。特に朝浴びると活動モードになる。
③身体を動かす
④昼寝は15〜20分にとどめる。
⑤入浴する。
⑥入浴して温まったらストレッチをする。
→ストレッチをしている間に冷えてきて眠くなる
⑦寝る前に明るい画面を見ない。
⑧寝る前にアルコール、カフェイン、ニコチンを摂取しない。
ホルモンや脳内物質は眠りにどう関係しますか?
メラトニンとコルチゾールの分泌
メラトニンの分泌
→メラトニンは22時頃から急増し、
コルチゾールの分泌
→コルチゾールは22時頃から緩やかに減少し、
コルチゾールはストレスホルモンとも呼ばれ、
これは一日の活動を始めるために心拍数、体温、血圧、
メラトニンやコルチゾールの分泌時間を考慮し、その生体リズムに合わせて就寝することは、自然に入眠する最良の方法です。
そう考えると、現代人の不眠を改善するのに最も欠如しているのは、メリハリの無さかもしれません。
暗くなってからも煌々と照らす照明があり、いつでもどこでも使えるモバイル機器があります。また、食事や入浴をしながら仕事のことを考えていたり、不安や悩みが床に就いても頭から離れないこともあるのではないでしょうか。
東洋医学から観る不眠
陰陽のバランスを重視する東洋思想
古からの東洋思想には、
すなわち、人の心も体も陰陽のバランスが大切ということです。
陰と陽にはそれぞれ反対の性質があります。
| 陰陽の特徴 | |
| 陰 | 陽 |
| 物質的・実質的 | 非物質的・実体がない |
| 形と構造を生み出す | エネルギーを生み出す |
| 成長と構築 | 破壊と変換 |
| 収縮 | 拡張・拡散 |
| 湿潤・水 | 乾燥・火 |
| 下方向・下からの作用 | 上方向・上からの作用 |
| 暗・影・夜 | 明・輝・日中 |
| 月 | 太陽 |
| 地球 | 天 |
| 静止 | 時間 |
| 空間 | 時間 |
| 平面的・詰まっている | 丸い・空洞的 |
わたしの入眠方法
個人的な話になりますが、わたしは中学生くらいの頃にこうすれば眠りにつきやすいという方法を見つけました。
床に就いて全身の力を抜きます。背中の接地面がやわらかくなり、そのなかにゆっくり沈んでいくような感覚をイメージします。はじめにお尻やお腹が沈み、最後に手足や顔が沈んでいきます。沈んでいくとなぜがそこは宇宙空間で、いつもだいたい手足や顔が沈む前に意識がなくなります。
この経験から、わたしは眠りは「陰」の性質が強いのではないかと考えています。
東洋医学的に、活発に動き回る交感神経優位は「陽」、まったりして落ち着いた副交感神経は「陰」というふうに言えるのではないでしょうか。
現代社会では、まだまだ生産性と効率アップが重視されています。
集中力を高める方法や短時間睡眠を推奨する情報など、交感神経が優位になり過ぎている感は否めません。
交感神経優位な状態をつづけられる能力は、万人に当てはまるわけではありません。
一人ひとり必要な睡眠時間は違いますし、交感神経が優位な人もいれば副交感神経が優位な人もいます。
大切なのは、バランスを意識しながら自分に合った生活リズムをつづけることです。
血が足りないと眠れなくなる?
立春が過ぎ、花粉の舞うこの時期は、不眠を訴える人も増加します。
春は生きものが動きはじめるとき。
人間も例外ではなく、心身ともに活動的になります。
そこで春とかかわりが深く、とても大切になる臓器が「肝」です。
「肝」にはたくさんの役割がありますが、
ところが、そもそも血が足りないと蓄えておくこともできません。
本来、冬はしっかり養生する季節ですが、そうならずに心身ともに動き過ぎていると血が不足してしまいます。
そのような状態のまま春を迎えてしまうと様々な不調があらわれます。
不眠もその一つです。
血の不足によって、熱が上昇し眠りが浅くなったり、
また、
ところで、「
そんな話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
しかし、血が足りない人が運動してさらに血を使うと、もっと血が不足して、
動きすぎも、動かなすぎも良くないのです。
結局、大事なのは陰陽のバランスということになりますね。
東洋医学な視点では、眠りについて「肝」と「血」
東洋医学については、麻生ホメオパスが分かりやすく書いてくれています。
こちら↓の記事も読んでみてくださいね。
不眠の原因にアプローチするためのレメディー
Acon.(アコナイト/トリカブト)
死にそうなほどのショック。
Ars.(アーセニカム/砒素)
不安が強いとき。死に対する大きな恐怖。
Arn.(アーニカ/うさぎ菊)
過去のトラウマが癒えていないとき。心と身体のケガの№
Kali-p.(ケーライフォス/リン酸カリウム)
ティッシュソルトの状態で摂ると、
Ferr-p.(ファーランフォス/リン酸鉄)
ティッシュソルトの第一人者であるシュスラー博士は、「
Alf.(アルファルファ/ムラサキウマゴヤシ)
紫色のきれいな花のマザーチンクチャー。消化不良、
Quer.(クエカス/ドングリ)
ナラの木のドングリのマザーチンクチャー。
マザーチンクチャーの第一人者のラデマッチャーは腫れた脾臓にQ
Yamab.(ヤマブドウ)
ポリフェノールを多量に含むヤマブドウのマザーチンクチャー。
ABOUT ME