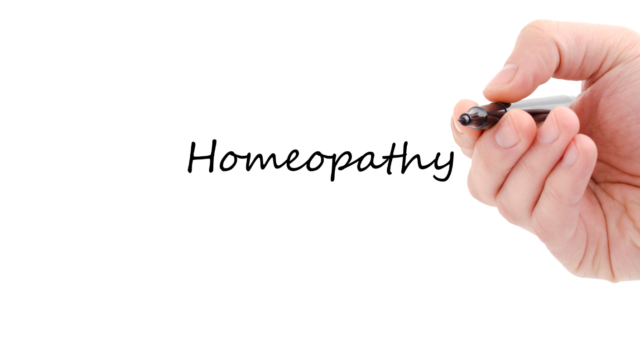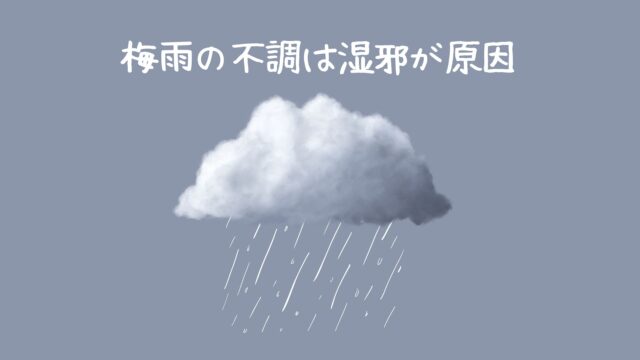Contents
はじめに:恩師の死から始まった、静かな問い
個人的な話から入ることを許してほしい。
先日、高校時代からお世話になっていた恩師が亡くなった。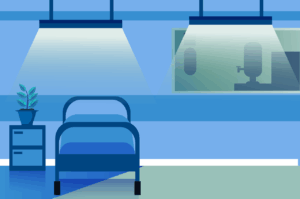
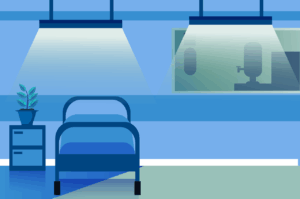
恩師といってもまだ50歳そこそこだ。
人生でいえば、ようやく折り返しを迎えたあたり。
だが、時間というのは、人の都合では止まってくれない。
彼が入院していると聞いて、仲間と見舞いに行った。
病室に入ると、全身に黄疸が出ていて、肝臓がもうかなり悪い状態だということはすぐにわかった。
けれど、会話は普通にできて、冗談も言って、笑っていた。
「元気そうじゃん」みんなそう思った。
でも今思えば、それは彼の最後の“日常“を守るための笑顔だったのかもしれない。
面会の時間が終わり、「じゃあ、また」
ふと振り返ると、彼はベッドの上で、静かに涙を浮かべていた。
そのときは、うまく言葉が出なかった。
でも、あとから思えば、あの「また」は、
“次はもうない”ことを彼は知っていたのかもしれない。
人は、案外あっけなく死ぬ。
けれど、死んでもおかしくない状況から生き延びる人もいる。
その違いはなんなのか。
強さなのか、運なのか、あるいは縁なのか……。
わからない。
ただひとつ言えるのは、
死はいつでも、わたしたちのすぐ隣にあるということ。
そして、そんな彼の死をきっかけに、わたしはある言葉を思い出した。
「メメント・モリ」
ラテン語で「死を想え」という意味のこの言葉には、
「だからこそ、よく生きよ」というメッセージが込められている。
その日から、わたしは静かに自分に問いかけるようになった。
「もし今日が人生の最後の日なら、私は何をするだろう?」と。
死を思うと、いまがくっきり見えてくる
死という言葉を口にすると、たいていの人は眉をひそめる。
「そんな暗い話やめようよ」と。
でも、死を意識するというのは、何も悲観的になることじゃない。
むしろ逆だ。
死を意識すると、生がはっきりと輪郭を持つ。
それはまるで、真っ暗な山の中でヘッドライトを点けるようなもの。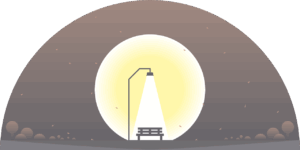
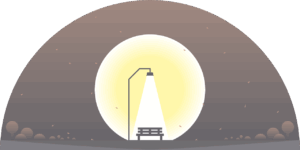
明るく照らされた外側には暗闇がある。
死を意識することは、あの暗闇を認識することに似ている。
もし永遠につづく人生があったら、
わたしたちは今日という日をここまで大切にしないだろう。
「また明日やればいい」「そのうち会えばいい」そう言いながら、
どれほどの時間を後回しにしてきただろうか。
でも、終わりがあると知っているからこそ、いまを丁寧に味わえる。
コーヒーの香り、風の音、誰かの笑顔。
その一つ一つが、
「もう二度とない瞬間」かもしれないと思うと、
自然と胸が熱くなる。
死を想うというのは、“いま“を生きるためのスイッチなのだ。
「死を想う」は「積極的に生きる」こと
哲学者のハイデガーが言っていた。
「人間とは、“死を意識して生きる存在“である」と。
死を意識することで、
人はようやく“どう生きたいか”を真剣に考え始める。
旅行の最終日がちょっと切ないように、

人生にも「終わり」があると思うと、
一瞬一瞬が特別に感じられる。
人生も、それと同じ。
永遠じゃないとわかるから、今が輝く。
メメント・モリ――
死を想うことは、つまり“積極的に生きる”ということ。
死を前にして、どう生きるか
人はいつか必ず死ぬ。
これは動かしようのない真理だ。
でも、その“いつか“がわからないからこそ、
わたしたちは怠けたり、迷ったりする。
「いつかやろう」と思っているうちに、

その“いつか“が二度と来ないこともある。
だからこそ、死を想うことには意味がある。
「自分の時間には限りがある」
そう感じた瞬間から、人は少しずつ変わっていく。
仕事のためだけに生きるのではなく、大切な人との時間を優先しようと思えたり。
やりたりことを「いつか」ではなく「今日」始めてみたり。
失敗を怖がるより、「やってみよう」と思えるようになったり。
死を意識すればするほど、いまの生にフォーカスできる。
「死を受け入れる」人の静けさ
病室での彼の姿を思い出すたびに、
考えることがある。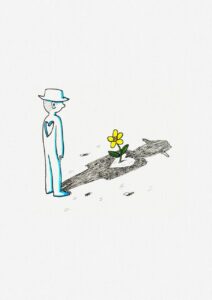
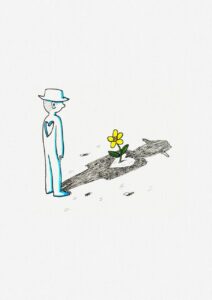
人は、自分の死を受け入れるとき、
不思議な静けさをまとう。
それは、諦めや絶望とは違う。
むしろ、すべてを受け止めたあとの「穏やかさ」だ。
たぶん彼は、残りの時間をもう恐れていなかった。
その代わりに、「いま」という瞬間を大切にしていたんだと思う。
誰かの死を通して学ぶのは、「生きることを恐れない」ということだ。
誰かを失うことで、人は強くなる
誰かを亡くすことは、痛みそのものだ。
でも、その痛みの中には、「生きる力」が隠れている。
亡くなった人の言葉や笑顔は、ふとした瞬間に思い出される。
夕暮れの空の色、街の匂い、音楽。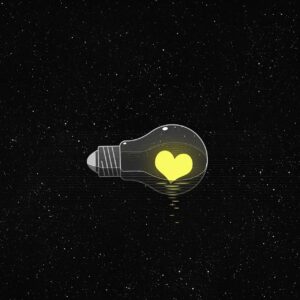
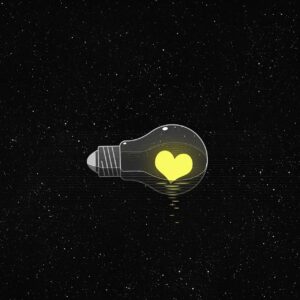
そのどれもが、その人の面影を連れてくる。
そして気づく。
その人は、姿はなくても自分の中に生きている、と。
“死“は、終わりじゃない。
形を変えて、別の形で続いていく。
だからこそ、
「生きているわたしたち」は、その人のことを想って生きていく。
「死を想う」ことで、生きる方向が見える
死を考えると、「どう生きたいか」が自然に浮かんでくる。

それは、立派な目標や成功のことじゃない。
誰かを笑顔にしたいとか、
好きなことをやってみたいとか、
心から「いいな」と思える瞬間を増やしたい。
そんな素直な思いだ。
死を想うことは、
「生きる意味を探すこと」ではなく、
「自分の心の声を聞き直すこと」だ。
死を想いながら、行動する生き方
死を考えると、人は行動的になる。
なぜなら、“やらない理由“が消えるからだ。
たとえば、

「いつか本を書きたい」「いつか旅をしたい」
その“いつか“は、いつ来るんだろう?
死を想うと、
「今やらなきゃ」という気持ちが強くなる。
やらない後悔より、やってみる勇気。
それが、生きることの本質なんだと思う。
実際、死を間近に感じた人ほど、
最後まで前を向いて生きる。
それは、命の時間を“使い切る“という生き方だ。
「死を想う」小さな習慣
死を意識すると言っても、特別な修行をすることじゃない。
むしろ、日常の中にほんの少し意識を向けるだけでいい。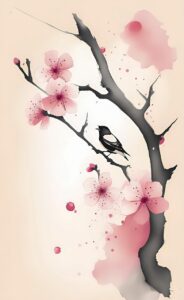
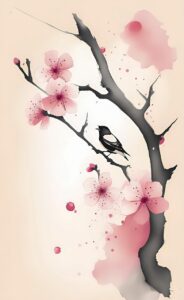
たとえば、
・朝、目が覚めたときに「今日も生きてるな」と思う。
・誰かに「ありがとう」を言えるうちに言う。
・花の散る様子を見て、「命の流れ」を感じる。
・苦しい日も、「これが最後の一日なら」と思って過ごしてみる。
そうやって日常の中に“死の意識“をほんの少し混ぜるだけで、生き方が変わってくる。
死を怖がるのではなく、
“生きる“を丁寧に味わう。
それが、メメント・モリの本当の意味だ。
積極的に生きるということ
「積極的に生きる」と聞くと、
何か派手なことをしなきゃいけない気がするけど、

そうじゃない。
それは、“自分の時間を自分で選ぶ“ということだ。
会いたい人に会い、
やりたいことをやり、
行きたい場所へ行く。
一見シンプルだけど、それを本気でやるのは案外難しい。
でも、死を想うと、
「やらない理由」がどんどん消えていく。
“後回しの人生“をやめて、
“いま生きる人生“に変える。
それが、積極的に生きるということだと思う。
おわりに:死を想うことは、生を愛すること
あの日、彼を見舞って病院を出たわたしは、
空梅雨の6月なのにすでに真夏のような空の下で、
当時の思い出に浸っていた。

彼はコーチとして、わたしは選手として、うだるような暑さのなかで、
汗と泥にまみれながら白球を追いかけた日々。
人は、簡単に死ぬ。
でも、その人が生きた証は、
簡単には消えない。
死を想うことで、わたしはようやく、
「生きる」といういことの意味を考え始めた。
それ以来、
日々の小さな出来事にも、
「ありがたさ」や「幸せ」を感じるようになった。
死を想うことは、悲しいことではない。
それは、いまを本気で生きるための、最も優しい哲学だ。
メメント・モリ。

死を想え。
それは、つまり今日を大切に生きよということ。
そして、今日という一日が、
少しでも誰かを笑顔にできたら、
それはもう、十分によく生きている証なんじゃないだろうか。
ABOUT ME