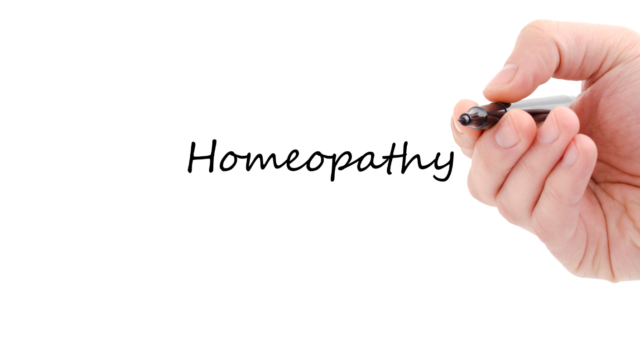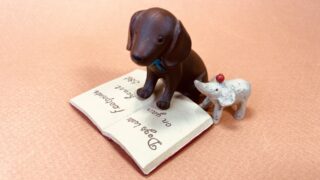はじめまして、栃木在住の自然療法家/ホメオパスの 中澤麻里 です。
自己紹介はこちら💁♀️。
暦の上ではもう秋ですが、まだまだ残暑が厳しい日が続いていますね。日中は日傘や水分補給が欠かせませんが、ふとした瞬間に涼しい風を感じることも増えてきました。
先日、クライアントAさんからこんな相談を受けました。
今回のテーマは、季節の変化を健やかに迎えるための「東洋医学的視点からみた養生」と「秋の養生におすすめの自然療法」です。
東洋医学が教える季節の変わり目
紅葉の秋、読書の秋、運動の秋、食欲の秋・・・
暑い季節から寒い季節の始まりにかけ、色々な顔を見せてくれる秋ですが、季節を表す分類法である二十四節気によると秋は、立秋(8月7日頃)から立冬(11月7日頃)までの3ヶ月を指します。
二十四節気は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けた中国で発明された季節の分類法。季節を表す言葉としてよく聞く、立春、春分、夏至なども二十四節気から来ている言葉です。
立秋【りっしゅう】[8月7日~22日頃]
残暑は厳しいけれど、暦の上では秋が始まる。
処暑【しょしょ】[8月23日~9月6日頃]
「処」は「収まる」の意味。夏の暑さが峠を越えて収まり、朝晩に秋の涼しさが感じられる頃。
白露【はくろ】[9月7日~21日頃]
草花に白い朝露がつく頃。秋になって夜が冷え込み、翌朝、草に結ぶ露が白く見えるという意味。
秋分【しゅうぶん】[9月22日~7日頃]
春分と同じく昼と夜の長さがほぼ同じに。先祖供養の日とされる秋のお彼岸もこの時期。
寒露【かんろ】[10月8日~~22日頃]
秋本番を迎えて野の草花に冷たい露が結ぶ頃。「天高く馬肥ゆる秋」、秋晴れの爽やかな日が続く。
霜降【そうこう】[10月23日~11月7日頃]
朝晩の冷え込みが厳しくなり、朝露が霜になって降り始める頃。山々の紅葉が美しい時期。
今は朝晩冷え込む白露【はくろ】の時期に当たります。
気温が下がると空気が乾燥し、呼吸器や免疫系にトラブルが起こりやすくなります。まだまだ暑い日が続いてはいますが、暑さばかりに気を取られていると、急な寒さが体調を崩すきっかけとなってしまうかもしれません。
秋は夏の暑さで強まっていた陽気(陽)が影を潜め、代わりに寒気や冷気(陰)が徐々に強まる陰陽転化の時期です。この大きな変化に身体も順応していく必要があるのです。
2000年前の医学書に学ぶ!秋の養生法
中医学の古典、『素問』には、秋の養生法が次のように書かれています。
早臥早起、与雞倶興。使志安寧、以緩秋刑。
収斂神気、使秋気平、無外其志、使肺気清。
此秋気之応、養收之道也。
逆之則傷肺、冬為飧泄、奉蔵者少。
「秋の3ヶ月を容平(容=もののかたち。平=安定する)という。強く冷たい風が吹き、地上の気は明るく透き通る。この時期は早寝早起きし、鶏とともに起きる。気持ちを穏やかに保ち、天地の秋の気の影響を和らげる。精神を引き締めて、平安を保つ。気持ちを外に向ける活発な行動は、やり過ぎないようにして、肺気を清涼に保つ。これが秋の養生法である。もしこの養生法に逆らうと、肺気が傷み、冬になると、飧泄の病気に罹り易くなる。すると、冬の「蔵気」に適応する能力が減少する。」
※飧泄(そうせつ):東洋医学における軟便や下痢を指す言葉
2000年前の医学書によると、秋は早寝早起きを心がけ、心穏やかに過ごし、冷えに気を付けると良いとのこと。なんだかあまり特別なことは言っていないような気もしますが・・・。普通に生活することがいかに大切か、よく分かります。
それでは秋の養生について、もう少し掘り下げてみましょう。
秋の不調は「肺」と「大腸」が原因?
五行説における秋と肺・大腸
東洋医学の五行説の中で、秋に属する臓は肺、腑は大腸であり、肺と大腸は表裏関係にあるとされています。
秋は気温が下がり大気中の乾燥が起こる時期。東洋医学では乾燥による害である「燥邪(そうじゃ)」の影響により肺を傷めやすいといわれています。
夏場に冷たいものを摂り過ぎ、冷房で体を冷やし過ぎてしまい、秋のはじめにだるさや胃腸の不調を感じたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
東洋医学でいうところの「肺」を傷めると起こること
呼吸器疾患(喘息、気管支炎など)の悪化
皮膚や粘膜に対する炎症や感染症等
「肺」に病変が生じると表裏関係にある大腸にも異常を誘発→便秘や下痢の症状に
秋におすすめの食材
肺を潤す代表的な食材
白キクラゲ・松の実・白胡麻・百合根・卵・牛乳・豆乳
肺を補い陽気を盛んにする食材
紫蘇・ニラ・生姜・大根・山椒・らっきょう・落花生・里芋・ネギ
梨
渇きを癒し熱を鎮める。
豆乳
肺・大腸を潤す。
良質なタンパク質を多く含む。カリウムが豊富。
はちみつ
肺・大腸を潤し、乾燥の改善に。
脾臓の虚弱を補う。
シナモン
温める作用が強い。
クコの実
肝・腎を補う。
潤す作用も強い。
秋の色は白!
なんだかおすすめ食材の中に、白い食品が多いような気がしませんか?
東洋医学では「秋の色」は白とされていて、白色の食材は肺を潤し養う作用があるといわれています。食材を選ぶときの参考にしてみて下さいね。
「夏の不調は秋のはじめ」に、「秋の不調は冬のはじめ」に。
季候による体調不良は季節を越えるタイミングで出ることが多いです。「冷え」に気をつけ、思い悩まず心穏やかに、そして規則正しい生活を。ぜひ、日々の暮らしで少し意識してみてください。
秋の養生のために自然療法ができること
おすすめのマザーチンクチャー
秋の症状に合うマザーチンクチャーを二つご紹介します。
Lob.ロベリア
喘息発作と呼吸困難。痰を出すことができない痙攣性の咳。
胃腸の問題を持つ喘息。
Rumx.ルメックス
冷気による喉のむずがゆさから起こる咳、喘息、気管支炎。
腸やのどの粘膜の乾燥と過敏さ、皮膚の痒み、蕁麻疹、消化器系に。
ペットボトルの水に10~20滴入れてちびちび飲むのがオススメ。
飲む時はシャカシャカと数回振って下さいね。
マザーチンクチャーって何?という方はこちらの記事をどうぞ→
伊藤真由美ホメオパス
家族の健康を守る最強ツール:マザーチンクチャーの活用法
おすすめのティッシュソルト
秋の症状におすすめのティッシュソルトはこちら
呼吸器・花粉症に:Ferr-p.、Kali-s.、Mag-p.、Nat-m.
消化不良・下痢に:Ferr-p.、Kali-p.、Nat-p.
便秘に:Ferr-p.、Nat-m.、Sil.
臓器の働きや基本的な代謝を保つために無くてはならない必須ミネラル。それをサポートしてくれるのがティッシュソルトです。一般的なサプリメントとは異なり、身体の中に足りなければ補い、多過ぎれば排出を促す働きかけをしてくれるので、安心してセルフケアに取り入れることができます。
ティッシュソルトについて詳しく知りたい!という方はこちらの記事をどうぞ→
伊藤真由美ホメオパス
バランスが健康の鍵!ティッシュソルトで体内のミネラルを整えよう その1
秋におすすめ!はちみつでスキンケア
はちみつは、実はスキンケアにもおすすめなのです。
水を抱え込む強い力
はちみつの中に含まれるグルコースは、水との親和性が非常に高く、お肌に塗ると皮膚からの水分蒸発を防いでくれます。
お肌にも美味しいフルクトース
はちみつに含まれるフルクトースが皮膚から浸透することによって、肌の新陳代謝アップが期待できます。
体の内側からも外側からも美味しいはちみつで、乾燥に負けない体づくりをしてみませんか。
おすすめの使い方:はちみつ化粧水
【材料】
はちみつ:小さじ1 グリセリン:5ml 蒸留水100m前後
【作り方】
はちみつ小さじ1をグリセリン5mlで溶かし、そこへ蒸留水を100ml程加える。
(はちみつによって粘度が異なるためお好みの濃度に調整して下さい)
※夏場は1週間以内、冬場は10日前後で使い切りましょう。
※グリセリンを入れると痒くなるという方や、混ぜるのが面倒という方は、少量を肌に塗って、その上から蒸留水をスプレーする方法もあります。肌に馴染ませた後、飽和脂肪酸のオイルを塗っておくと乾燥知らずになれますよ。
まとめ
いかがでしたか?今回は東洋医学的視点からみた秋の養生と自然療法でできるおすすめの養生法についてお話しさせていただきました。
なんとなくだるい・・・。毎年同じ季節に起こる症状がある・・・。
観察して紐解いてみると、意外と解決策は身近にあるかもしれません。ピンときたものがあったらぜひお試しくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
お肌にも身体にも安心なはちみつはこちらでも販売しております。