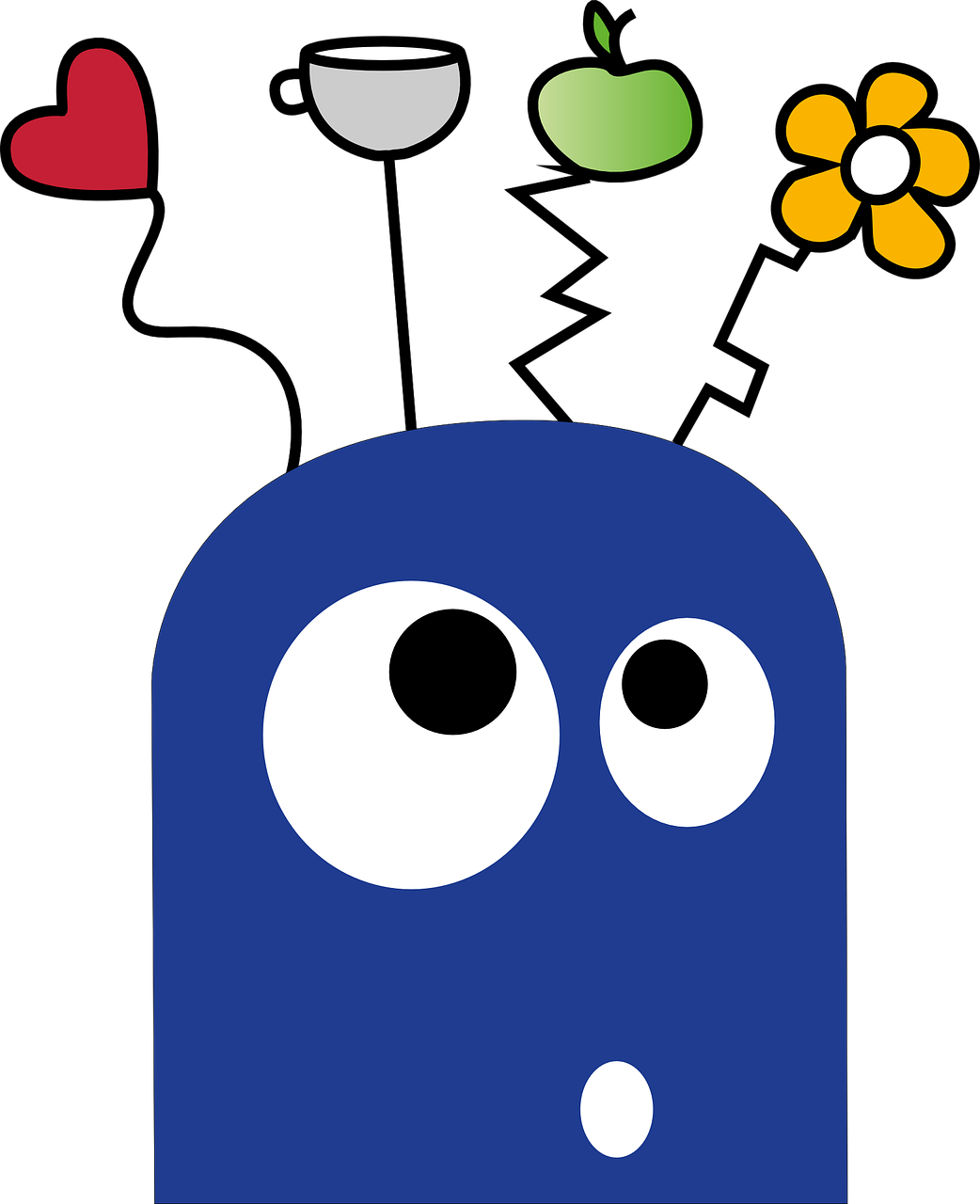どうしてわたしたち人間は肉体をもっているのでしょうか?
粘土細工を作るように、たまたま神様の気まぐれで、人間という生きものが出来上がったのでしょうか?
いえいえ。きっと肉体をもって生まれてきたのには理由があるはず。
それは、とても重要で大切なもののはずです。
人が肉体を持って生まれてきたのには、
とても深い質問だ。人が肉体を持って生まれてきた意味については、宗教、哲学、
Contents
人が肉体を持って生まれてきたワケ
1. 経験するため
肉体があることで、痛みや喜び、愛、喪失、努力など、「体験」をすることができる。
肉体は感覚器官を通じて、世界を感じ、学び、
2. 魂を成長させるため
いくつかのスピリチュアルな伝統では、
肉体という制限があるからこそ、忍耐、愛、
3. 物質世界を体験するため
肉体がなければ、物理的な世界(自然、他者、ものづくり、
この世界の美しさや重みを、実際に「生きる」
4. 自己を知るため
肉体を持つことで、自分自身を外界と区別でき、「自分とは何か」
苦しみや限界を通じて、本当の自分に目覚めるため、
5. 使命を果たすため
何か特別な役割や使命を持ってこの世に来ているとする考え方もある。
肉体はその使命をこの世界で実現するための道具だという捉え方。
ただ、この問いに「正解」はない。自分なりに意味を見出していくこと自体が大切な旅なのだ。
心の状態は、肉体を動かすことでどんなふうに変化するの?
とてもいい質問だ。心の状態は、肉体を動かすことで大きく変化するぞ。以下に簡単にまとめておいた。
肉体を動かすと心の状態が変化する
1. 身体を動かすと脳内の化学物質が変わる
運動すると、エンドルフィン(幸福ホルモン)やセロトニン(
これによって、不安や落ち込みが軽減され、
2. 姿勢や呼吸が心に影響する
背筋を伸ばすと、自然と自信や元気が出る。深い呼吸をすると、心が落ち着く。逆に、猫背になったり浅い呼吸を続けていると、
3. 身体を動かすことで思考が変わる
散歩や運動をすると、頭の中が整理されたり、
モヤモヤした気持ちも、
これは「体が流れを作る→心も流れに乗る」
4. 肉体を通じて「今ここ」に戻れる
ジョギング、ダンス、呼吸法などに集中すると、
つまり簡単に言うと、心を変えたいなら先ず体を動かすと早いということだ。
じゃあ、なんでジョギング、ダンス、呼吸などに集中すると、不安から離れて「今この瞬間」
それについては、さらに深く掘り下げてみよう。
ジョギング、ダンス、呼吸に集中すると「今この瞬間」
簡単にいうと、 脳の注意が「思考」から「感覚」へ移るから。
普段、人は頭の中で過去の後悔や未来の不安を考え続けている(
でも、ジョギング、ダンス、呼吸法のような「リズム運動」
感覚に意識が向くと、思考の堂々巡りがおさまってくる。
感覚は「今」しか存在しないので、結果的に「今ここ」を感じられるようになる。
つまり、肉体のリズムに心が引き寄せられることで、
一定のリズム運動は心にどんな影響を与えるか?
1. 自律神経を整える
リズム運動(一定のペースで体を動かす運動)は、
心拍や呼吸が整うので、ストレスが減り、
2. 脳内でセロトニンが分泌される
リズム運動を一定時間続けると、セロトニン(
セロトニンは「心の安定剤」とも呼ばれ、
3. トランス状態に近づく
同じリズムで長時間動き続けると、いわゆる「ゾーン」や「
頭で考えるのではなく、感覚で世界と一体化したような感覚(=
これによって、自己超越感や深いリラックスが得られやすくなる。
まとめると、 リズム運動は、心の嵐を鎮めて静寂に導く働きがあると言える。
じゃあ、リズム運動で幸せになれるってこと?
そうとも言える。リズム運動はとても自然に心を満たすことができる方法なんだ。リズム運動をすると、脳内のセロトニン(心を安定させる)や、
リズム運動で幸せになる
【1】軽めのジョギング(特に自然の中で)
ポイントはペースを競わないこと。心拍が「少し上がるけど会話できるくらい」の軽い強度がベスト。木々の揺れや風、鳥の声など、
【2】音楽に合わせたダンス
音楽のビートに合わせて体を動かすと、脳が「一体感」
【3】リズミカルなウォーキング(マインドフルに歩く)
「1、2、1、2」
【4】呼吸法(リズミック・ブリージング)
たとえば「4秒吸う・4秒止める・4秒吐く・4秒止める」
【5】太鼓やドラムを叩く(リズム演奏)
ドラムやジャンベ(アフリカの太鼓)を叩くときの「リズム感」
まとめると、好きなリズムに乗って、自由に体を動かすことが、
へぇ~。じゃあ、例えばジョギングとウォーキングではどっちがより幸せを感じられるの?
結論からいうと、人によって違うけれど、一般的には、ウォーキングは「じんわりした幸福感」(安心・安定・
ジョギングとウォーキングではどちらが幸福?
ウォーキングの幸福感
リズムがゆっくりなので、自律神経(特に副交感神経=
「自然と一体化してるなぁ」とか「心が澄んでいくなぁ」
瞑想的な効果もあり、深い安心感・満たされ感につながりやすい。
ジョギングの幸福感
強度が上がるので、エンドルフィン(
「体が軽い!」「生きてるって感じる!」みたいな、
ある程度のペースでリズムに乗れると、気持ちが「上向き」
じゃあ、どっちがいいの?
キミが今ほしい幸福感で選んだらいいんだよ。
こんなときはウォーキング orこんなときはジョギング
★心が疲れているとき or 元気を出したいとき
★深く落ち着きたいとき or 気分を一気に変えたいとき
★自然の中でゆっくり感じたいとき or スカッと達成感を得たいとき
さらにいうと、ウォーキングからスタートして、
交感神経優位のときにリラックスしたいときはどうなの?
鋭い質問だ。交感神経が優位(=興奮・緊張モード)
交感神経→副交感神経へ段階的に移行する
1. 軽いリズム運動で「興奮」をいったん受け止める
例えばウォーキング(やや早歩きでもOK)からスタートし、「1、2、1、2」とリズムを意識して、
2. 呼吸を「だんだん」深くする
歩きながら、少しずつ呼吸を長くしていく。
例:「4秒吸って、6秒吐く」を意識する。(
3. ペースを徐々に落としながら、静かな感覚に入っていく
歩くスピードを少しずつゆっくりにしていく。最後は、立ち止まって深呼吸だけでもいい。
なんでこの方法がいいの?
体の「今、興奮してる」という状態を否定せずに認めるから、
逆に副交感神経優位のときに、
この「逆パターン」もすごく大事だ。これもコツがあって、急にガツンと刺激を入れないで、じわじわ交感神経を活性化させるのが一番スムーズなんだ。
副交感神経→交感神経へ段階的に移行する
1. 呼吸を意図的に速める
ちょっと浅め&テンポよく呼吸します(例:
呼吸が速くなると、自然に交感神経が活性化してきます。ここで「目を開いて光を感じる」とさらに効果UP。
2. テンポのいいリズム運動をする
軽いジャンプ(その場でぴょんぴょん跳ねる)や、
リズムを速くすることで心拍数が上がり、
3. 目線を少し上げる
目線を下げると副交感神経寄り、
4. 短い目標を決める
「まずは3分だけ動こう」とか、「まずは机の上を片付けよう」
呼吸を速める → テンポのあるリズム運動 → 目線を上げる → 小さな行動を始める。この流れで、
男性と女性では幸せの感じ方って異なるの?
深い質問だ。答えは、「基本的な傾向としての違いはあるが、
男女での「幸せの感じ方」の違い
★女性は「共感」「つながり」による幸福感を感じやすい
誰かとの「共感」や「心の交流」があると、オキシトシン(
たとえば、誰かと一緒にリズム運動をしたり、
★男性は「達成」「挑戦」による幸福感を感じやすい
目標を設定して、それを達成したときにドーパミン(やる気・
たとえば、走り切った、登り切った、スコアを更新した、などの「
★なぜ、こういう違いが出るのか?
これは生物学的に見ると、女性は「仲間と協力して生きる」ことに適応してきた歴史。男性は「狩りや競争に勝つ」ことで生存してきた歴史が背景にある。
だから、
でも、個人差もかなり大きい。
たとえば、目標達成型の女性もいれば、共感重視型の男性もいる。
性別だけでなく、その人が今どんなフェーズにいるかでも、
たとえば、すごく頑張ってきた人が「癒し」を求めてるときは、
つまり、「今の自分がどんな幸せを欲しているか」
女性は「共感・つながり」から幸せを感じやすく、男性は「達成・
幸せを感じていると病気になりにくいの?
モチロン!とてもなりにくくなる。かなり多くの研究で、「幸福感の高い人は、免疫力が高く、病気になりにくい」ということが分かっているんだ。
幸せを感じていると病気になりにくいワケ
1. ストレスホルモン(コルチゾール)が減る
幸せを感じると、体内でストレスホルモンが自然に下がる。
コルチゾールが減ると、免疫細胞(リンパ球など)が活性化して、
2. 免疫系を調整するホルモンが増える
幸せな感情を持つと、セロトニンやオキシトシンなど、体を「
これらが自然治癒力や再生力を高めてくれるので、
3. 自律神経がバランスよく働く
幸せな感情は、自律神経(交感神経と副交感神経)
特に副交感神経が安定することで、内臓の血流が良くなり、
4. 良い行動習慣が自然に増える
幸せを感じている人は、自然とよく笑う・よく眠る・よく食べる・体を動かす、などの健康的な習慣をとりやすくなるので、
結論、幸せを感じること自体が、最高の健康法というわけだ。しかも、無理にポジティブになろうとしなくても、「小さな幸せを感じる」
そっかー。心から「今日ちょっと楽しいな」とか「気持ちいいな」
それはただの気分だけじゃなく、
【1】「今この瞬間」に注意を向ける
幸福感は、頭で「幸せになろう!」
大事なのは、今感じている「小さな快」に気づくこと。
たとえば…太陽の光があたたかい・コーヒーの香りがいい・風が心地いい・呼吸がゆっくりできている。こういう微細な感覚に「わぁ、いいな」と意識を向けると、
【2】「感謝のメモ」をつける
夜寝る前に、「今日よかったことを3つ」
小さなことでOK!例:「道端の花がきれいだった」「あの人が笑顔だった」「
この習慣は、脳の「よかったことを探す回路」を強化する。習慣化すると、普段から「幸せ」
【3】リズム運動を取り入れる
歩く、軽く体を揺らす、ダンスする、深呼吸する。
一定のリズムで体を動かすと、セロトニン(
【4】好きなものにちょっとだけ触れる
好きな音楽を1曲だけ聴く・好きな香りをかぐ・好きな場所の写真を見る。
こういう小さな「好き」体験も、幸福感を育てます。
ポイントは、「長時間やる」よりも短くても濃く感じること!
【5】自分をほめる
何かできたとき、小さなことでも「よくやった!」「今日も生きた、すごい!」 と、自分に声をかける。
脳は自分からのポジティブなフィードバックにもちゃんと反応しま
【まとめ】
今感じている小さな快感に気づくこと。
リズム・感謝・好きなもの・自分ほめ、
これを無理なく続けると、「がんばって幸せになろう」としなくても、
肉体から幸せを感じることは、目に見えるものをベースにして、目に見えないものを実感する錬金術のようなものです。
それは土の時代から風の時代へシフトしてきた「今」と言うこともできるでしょう。
ABOUT ME